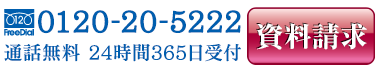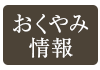四十九日法要の段取り

葬儀が終わって、ホッとしたのも束の間、
四十九日はすぐにやってきます。
「四十九日法要」は、葬儀後に行う初めての法要です。
お亡くなりになった日を1日目と数えて49日目にあたる日に行います。
1か月半というと結構時間があるように感じますが、葬儀の後は手続きなどもあり、その合間をぬって準備しなければいけないため、余裕をもって早めに行うことをお勧めします。
※地域慣習や状況等によって、多少異なります。
法要の日取り・場所を決める
日時を決める際には、希望日程をご住職と相談しながら、できる限り多くの人が集まれる日を優先するため、本来の四十九日より前の土日などがよく利用されます。 49日目を過ぎてから行う事は故人様の魂を待たせることになるため、避けるようにしましょう。
法要や会食の会場は日程によっては利用できない場合もあるため、葬儀が終わってすぐに調整を始めるのがいいですが、遅くとも1ヶ月くらい前には決めておきましょう。
★当社でも承ります(会食会場)

案内状の作成/連絡
法要日時と場所が決定したところで、参列してほしい方へ往復はがきなどで案内を出し、出欠の有無を確認します。
基本的には郵送でのご案内がよいと思いますが、親族のみで気遣いの無い場合などは、電話での確認でも良いというご意見もあります。
★当社でも承ります
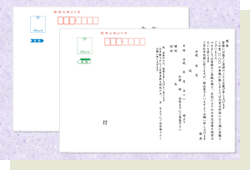
本位牌
葬儀の際に使用した白木の位牌は、四十九日までの仮位牌です。
法要を機に、黒塗りや唐木などの本位牌に作り直し、当日ご住職が魂を移すお経を読んでくださいます。
本位牌は作成に多少お時間がかかるので早めに準備しましょう。
★当社でも承ります

返礼品の用意
葬儀と同じように、法要の際もお香典(四十九日からは「御仏前」になります)をいただきますので、返礼品を人数分(お香典の数分)用意します。
会食後、解散のときにお渡ししましょう。
★当社でも承ります

墓誌への戒名彫り
一般的には四十九日法要にあわせて納骨しますので、日程と頂いた戒名を石材店に伝え、彫刻してもらいます。
★当社でも承ります

生花(本堂用、墓地用)
★当社でも承ります
供物(果物・お菓子)
★当社でも承ります
お線香
★当社でも承ります ご注文はこちら
お布施
当日の流れ
法要は、以下のような流れで進めます。
- ❶
現地に集合 - ❷
法要
(読経・焼香・法話) - ❸
墓地へ移動し
納骨 - ❹
会食場所へ移動し
お食事 -
解散
服装
男性・女性ともに遺族は喪服を着用したほうが良いでしょう。
参列者は、略儀喪服や地味な服装でもかまいません。
当日の持ち物
当日は以下の持ち物を忘れないようにしましょう。
お塔婆(葬儀で使用したもの)
お骨
生花(本堂用・墓地用で2対)
お線香
お布施
返礼品